実際に使用していたカルタ(百人一首) の説明 (例)です。
説明どうしようって時に実際に筆者がメモしていたものです、何かの参考になれば。
人に説明するための参考マニュアル
対戦は一対一で小倉百人一首100枚の内から50枚を取って残りは箱にしまいます。25枚ずつを左右の幅は78センチ、間は3センチあけてならべます。これが基本の形です。
ここにある50枚の札の場所を試合では15分で覚えます。
その中で最後の2分は素振りしていいことになっています。
読まれた札を取ることで自分の陣の札を減らしていきます。
先に自分の陣の札を0枚にした方が勝ちです。
・取ったあと
今のはこちらの取りです(取った方を示す)
①相手の陣を取ったことになるので1枚相手に送ることが出来ます。
②自分の陣を取ったので、自分の陣の札が1枚減ります。
今の札は「め」で取れます。
一字で取れる札は一字きまりと言って、7枚あります。(その他読まれるたびに、どこまで読めば取れるか、何枚あるかを説明)
・友札を持っている札が読まれた時
今の札は「あらざ」でとれます。「あら」まで同じ音の「あらし」という友札があるため、「あら」まででどちらの札かはわかりません。
・決まり字が短くなった札が出た時
いまの札は本当は「かぜそ」まで読まれなければ取れませんが、前に「かぜを」という(友)札が既に読まれているため、「かぜ」のみで取ることができます。
・から札のとき
そのから札で決まり字がどう変化するかを説明。
・運命戦になりそうな時
お互い残り1枚の状態を運命戦といいます。
自分の陣の札が出た方が有利であるため、ほとんどの場合、運によって決まります。
«注意»
札が読まれ始めたら説明が途中でも中断すること。
こめんと
2019/11/1最終更新
なかなかマイナーな競技だからこそ、
実際にやっているところを見せながらフラッと解説を聞けるのは結構いいのではないでしょうか??
以上っ

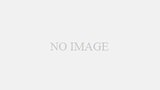

コメント